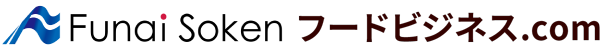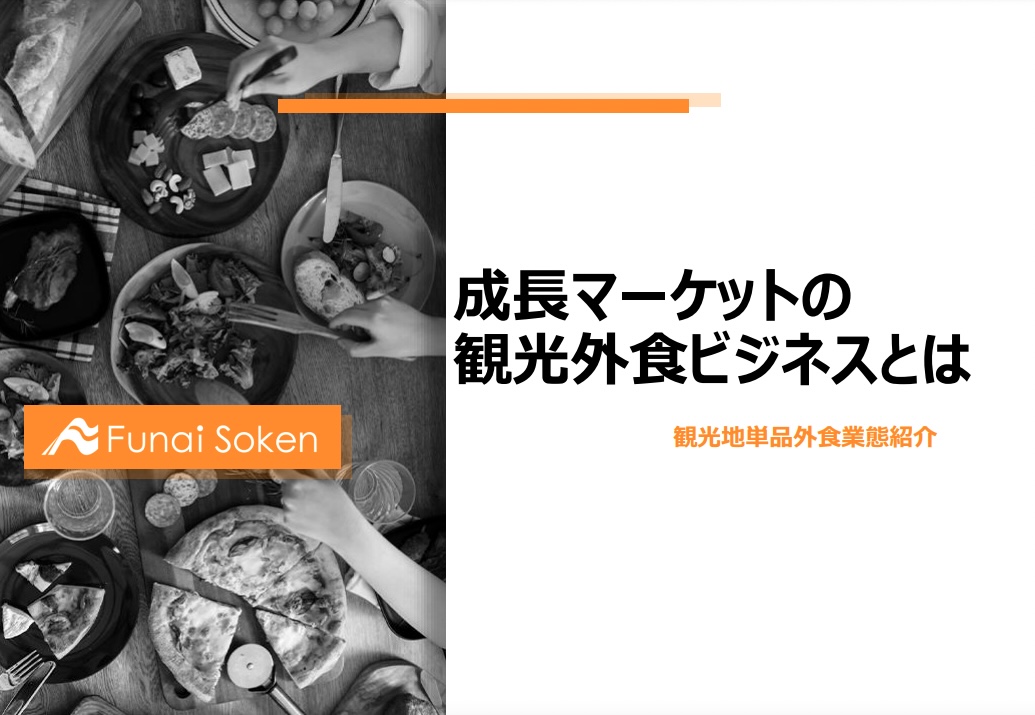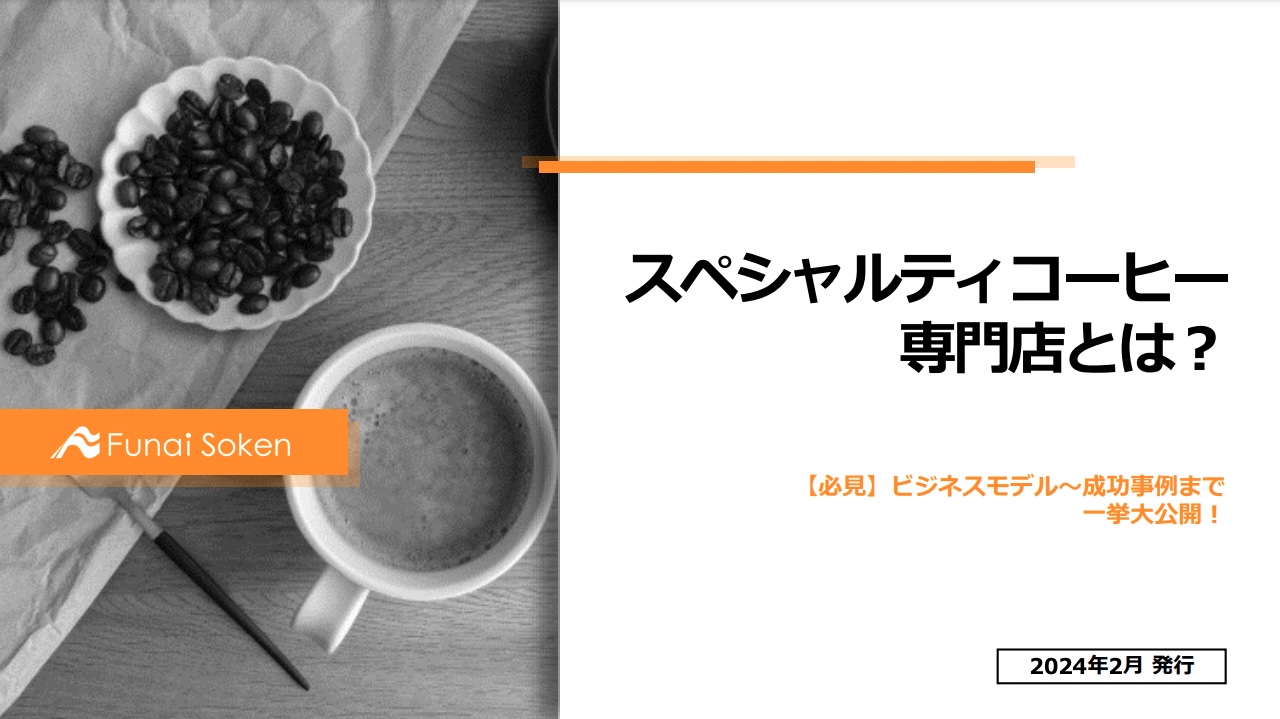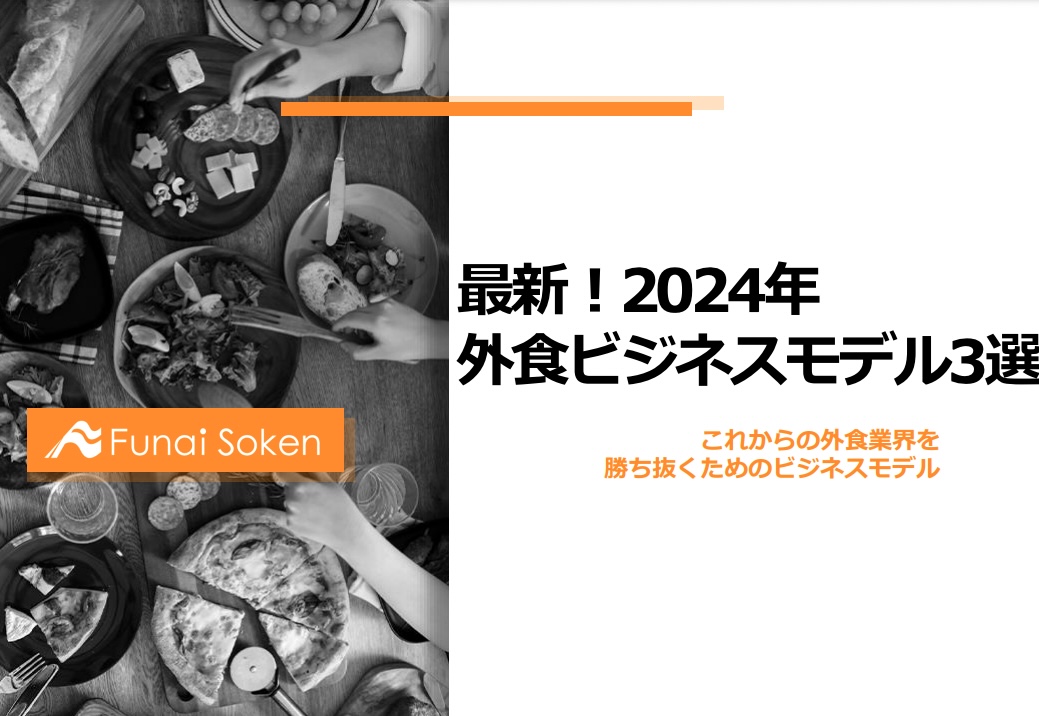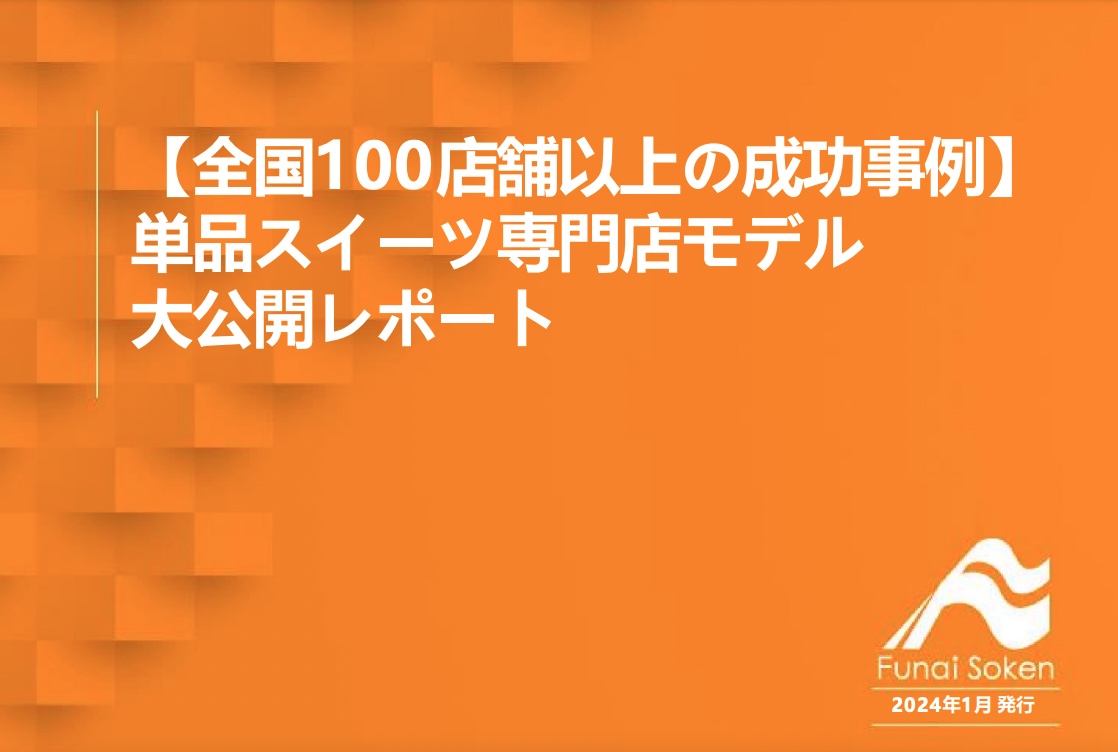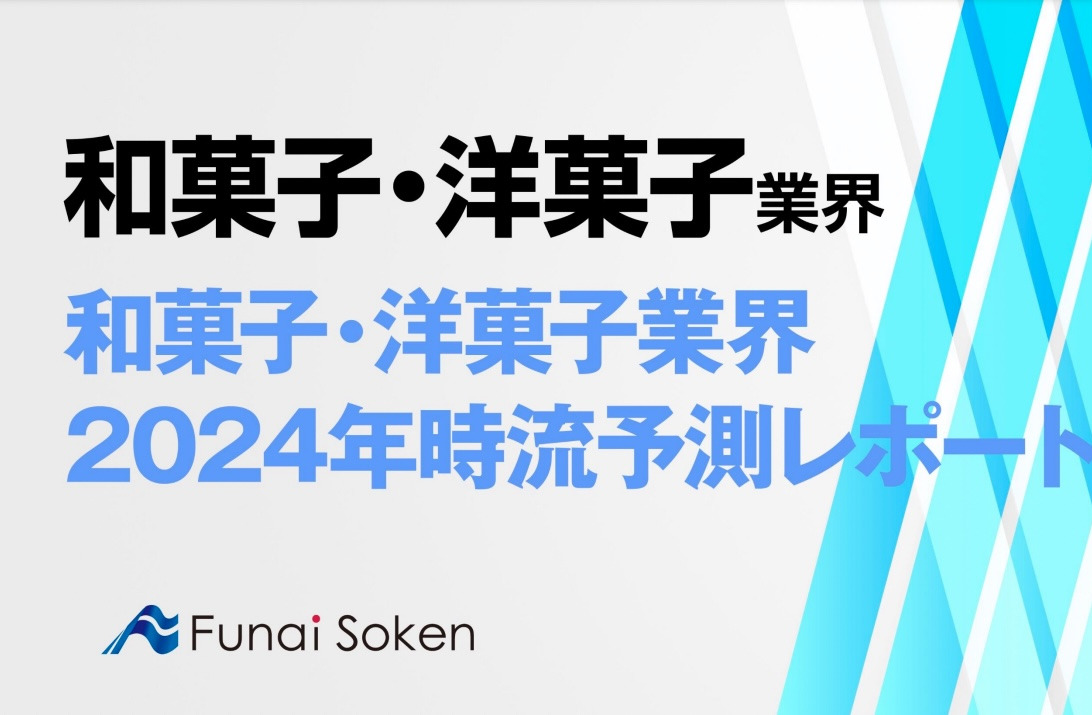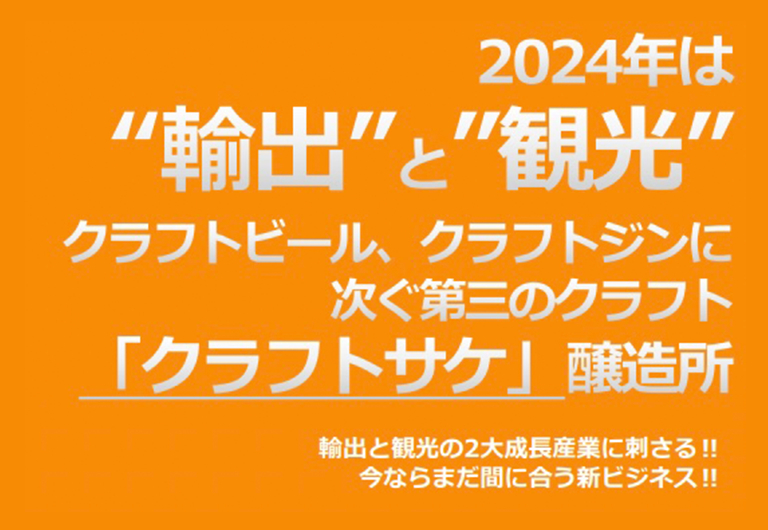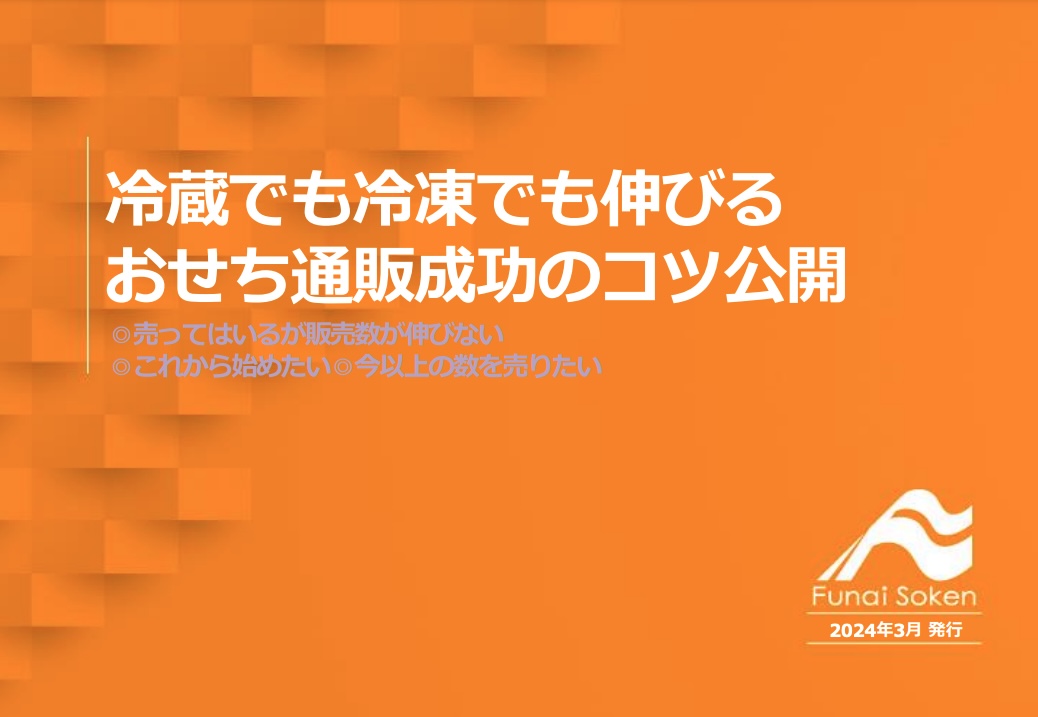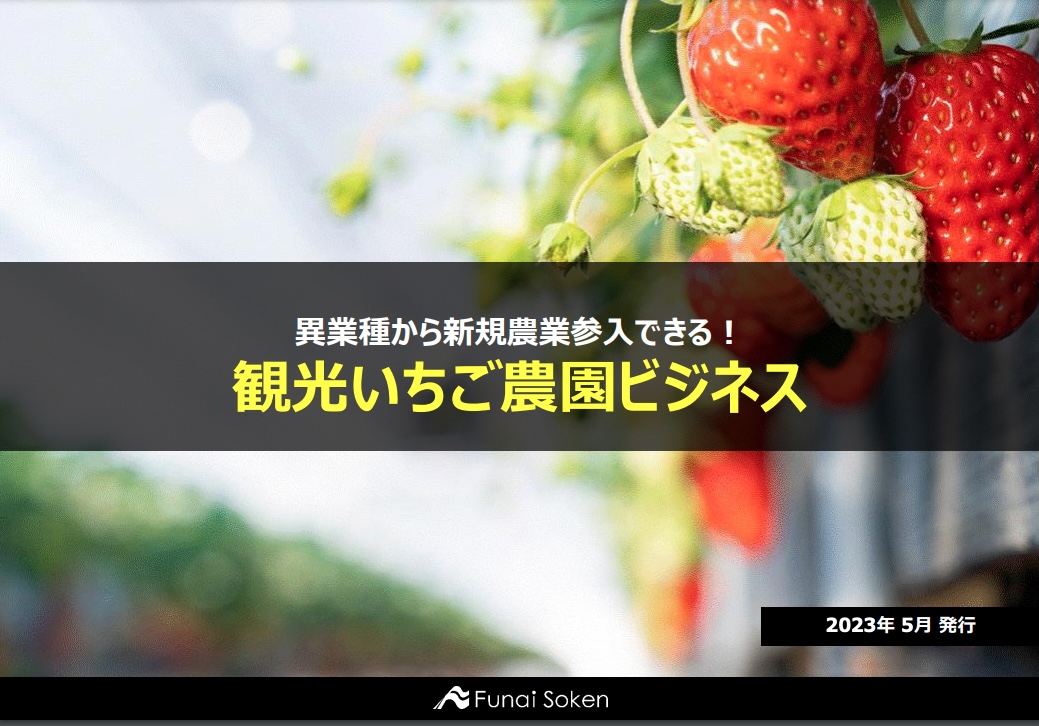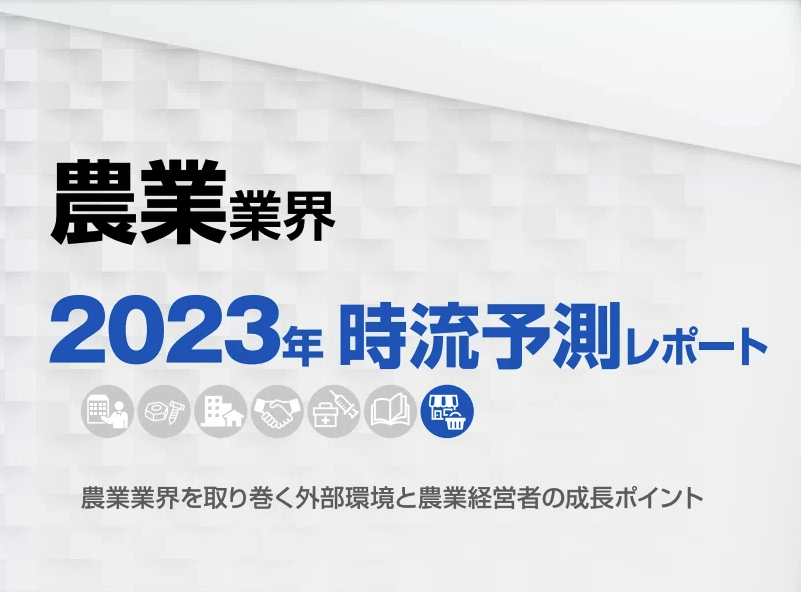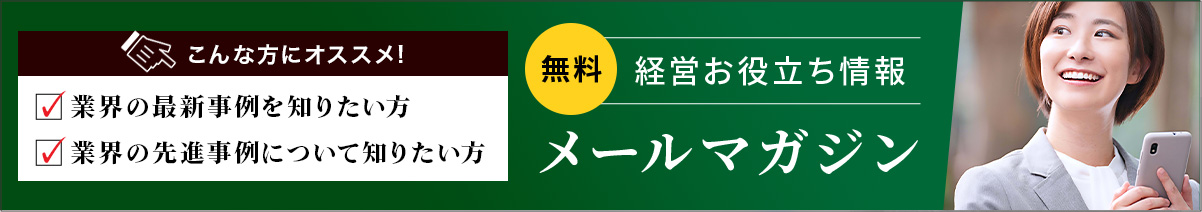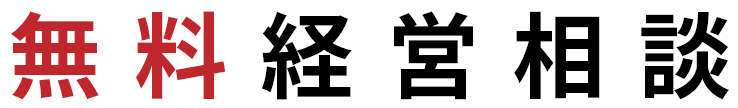国内最大級の経営コンサルティング会社の「フードビジネス専門サイト」

コンサルタント一覧
- 外食・中食ビジネス
- スイーツ&ベーカリービジネス
- 食品メーカービジネス
- 農業ビジネス
- 行政・地方自治体コンサルティング
外食・中食ビジネスの業績向上なら私たちにお任せください!
スイーツ&ベーカリービジネスの業績向上なら私たちにお任せください!
食品メーカービジネスの業績向上なら私たちにお任せください!
農業ビジネスの業績向上なら私たちにお任せください!
行政・地方自治体コンサルティングの業績向上なら私たちにお任せください!